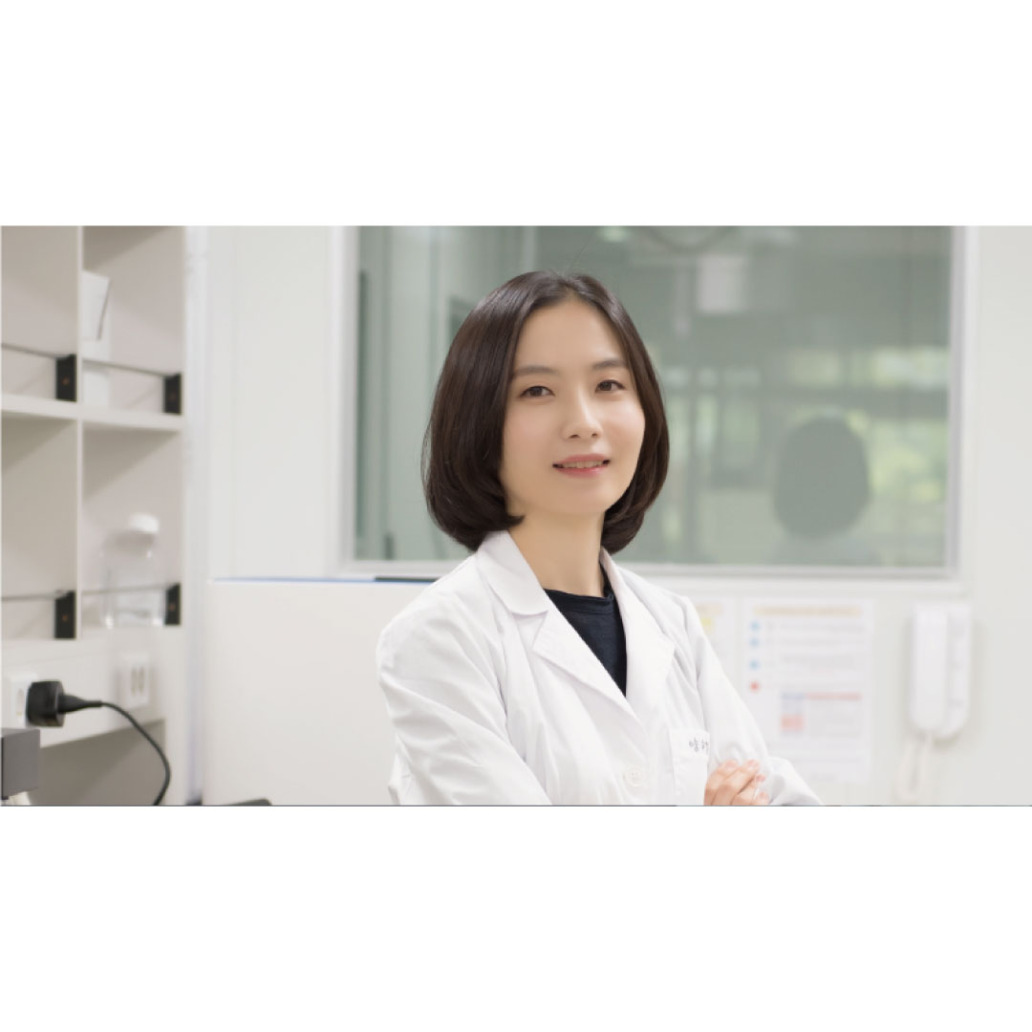[インタビュー]ヤン・ヒョンジョン国際脳教育総合大学院大学統合ヘルスケア学科学科長
瞑想がグローバル企業を中心に健康管理の次元を超え、
新たな人材育成法として注目されています。
韓国では、脳教育瞑想の効果を国際ジャーナルに着実に発表してきた韓国脳科学研究院をはじめ、
KAIST瞑想科学研究所の設立に続き、大韓瞑想学会が発足するなど、
科学界、医学界の瞑想研究及び活用もますます高まっています。
2020年から韓国脳科学研究院の副院長を務めている
ヤン・ヒョンジョン国際脳教育総合大学院大学統合ヘルスケア学科の学科長に会い、
瞑想について話を聞きました。
神経科学の側面から瞑想の効果、脳への影響などを研究しているヤン教授は、
東京工業大学生命工学科で生命情報(Biological Information)を専攻し、
学士、修士課程を終えて博士号を取得しました。
その後、2010年から2017年まで基礎科学分野の世界的な研究所である
イスラエルのワイズマン研究所で研究員として在職し、
2017年に国際脳教育総合大学院大学の教授に就任し、
2020年から韓国脳科学研究院の副院長を兼任し、脳教育瞑想研究に取り組んでいます。
2021年からは新たに新設された統合ヘルスケア学科の初代学科長を務めています。
以下は、ヤン教授とのインタビューです。
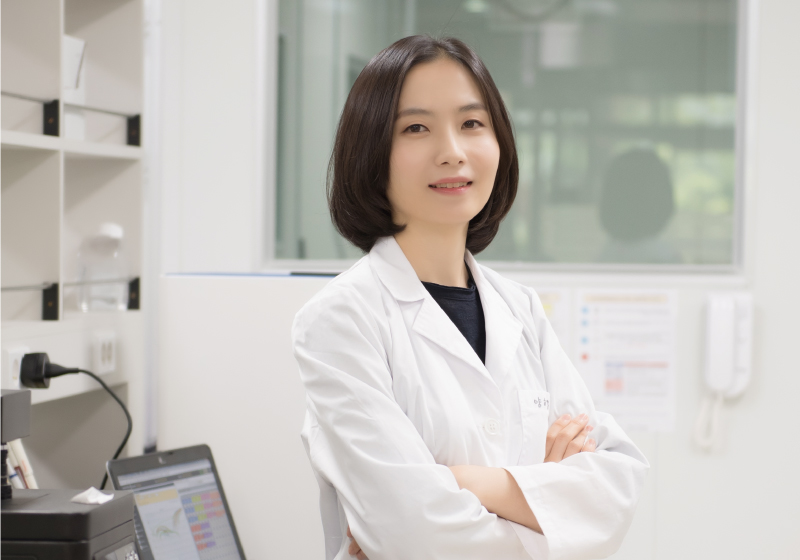
Q. 世界的な研究所であるイスラエルのワイズマン研究所で
分子神経科学分野の研究をされ、
現在は瞑想と統合ヘルスに関する研究をされていますが、
少し異色の経歴をお持ちですね。
なぜ研究分野をこのように変えられたのですか?
私は大きく分けて神経科学の分野で研究をしています。
以前は、細胞、分子、遺伝子レベルでの研究が主でしたが、
人間の個体レベルでの脳は、
一種類の分子や細胞が調整していると言うにはあまりにも多様な要素が影響しています。
一つの種類の分子や細胞を一つの楽器とすると、
脳はその多くの楽器が集まってオーケストラを演奏してアウトプットが出るものとも言えます。
脳を勉強して研究してきて、自分自身や周りを見ていると、
すべての思考、感情、行動が脳から出てくるのですが、
それを調節するのが意志とは違って難しい時が多いようでした。
何かをしたいときに怠惰な気持ちになったり、
ある状況で感情的になって理性的に判断できないこともありますし、
過去の傷がトラウマとして残り、人生を正しく生きるのが難しいこともあります。
すべては脳から出てくるので、この脳をうまく調節すれば、
このような人生の問題は解決するのではと思い、
どうすればいいのかということを考えるようになりました。
薬は急性期の治療には必要ですが、解決したい問題によっては
長期的に根本的な解決にならない場合があります。
例えば、うつ病の人に抗うつ薬が一時的な助けにはなりますが、根本的な解決にはならないように。
そこで、最終的には自分の脳をうまく調整する方法が何かないかと考えた結果、
人生と自分自身について新しい視点を提示する瞑想の要素に着目し、
研究テーマに発展させることになりました。
実は神経科学の分野では、アメリカやヨーロッパでは瞑想がたくさん研究されています。
アメリカのNIHでも補完統合健康センター(National center for complementary and integrative health)を設置し、政府レベルで支援しています。
脳と体はつながっていて、体で運動をすると脳に影響を与え、
瞑想をすると意識の状態を変えて身体が変わります。
体と心が相互作用するのです。瞑想が私たちの体に与える影響を
神経科学的な観点から今後研究していきます。
Q. 脳をうまく調整して人生を変えることに興味があり、
瞑想に関する研究を始めたということですね。
では、研究してみていかがですか。
瞑想によって本当に人の脳は変化するのでしょうか?
瞑想によって人の脳が変化するということは、
たくさん研究されていて、多くのことがわかっています。
瞑想に関連して脳がどのように変化するかについてまとめた論文を見ると、
特に注意調節、感情調節、自己認識に関連する脳の部位が変化することが知られています。
韓国脳科学研究院で2013年にソウル大学病院と共同で行った研究で、
瞑想が成人の脳の内側前頭葉などの白質と灰白質の厚さの変化と関連があることが報告されました。
Q. 脳教育瞑想が遺伝的な違いも解消できるという
研究結果もあると聞きました。
人の性格は脳神経学の観点からどのような意味がありますか?
人の性格は他のすべての特性と同様に、脳の神経網を私たちが認知できるように発現した形です。
私たちの脳は変化できる可塑性があるため、性格で表現される脳の神経網に相当する部分も
トレーニングで変えることができるということが示唆されています。
2016年、Psychiatry Investigに発表された研究脳教育瞑想の効果によると、
遺伝的背景によって外向的な性格か、神経症的傾向があるか、
喜びを追求する傾向が多いか少ないかなどの性格特性が、
脳教育運動法による訓練によって、社会性に有益な方向に改善されたことを示しました。
つまり、外向性が増加し、神経症的傾向が減少し、オープンな心が増加し、
喜びの追求が増加し、行動を抑制する傾向が減少しました。
特に、この変化は、個人が周囲と付き合う社会性が増加することを意味します。
これは、脳教育瞑想が社会で活発に活動できる方向に脳を変化させると考えられます。
Q. 社会性が増加するということは、
脳教育瞑想のもう一つの重要な効果ではないでしょうか?
脳教育は国際ジャーナルに2010年以降、主に健康と関連して報告されましたが、
脳教育瞑想は健康の効果とともに教育にもプラスの効果があります。
健康面で脳教育は多くの効果がありますが、
その中でもストレス管理能力を優れた効果の一つに挙げることができます。
ストレス管理とは、自分自身の感情を調節できる能力を指します。
2013年、「SCAN」誌に掲載された、
ソウル大病院と韓国脳科学研究院が共同で研究した結果によると、
脳の構造的側面から見ると、特に感情を調節する脳の前方部部位で
瞑想によって構造的な変化が起こりました。
また、脳教育によってストレスの減少が現れる点を考慮すると、
脳教育瞑想によってストレスの状況で感情を調節して
自分を調節する能力が向上したことを示唆していると見ることができます。
教育面では、脳教育は人格を涵養させることに大きな効果がありますが、
その過程で見られる特徴の一つは、自己観察力の増加です。自己内省とも言われますが、
個人にとってどんな良い点があるかというと、
例えば自分を客観的に見ることができるようになります。
その訓練を続けることで、感情を混ぜずに自分を判断できるようになり、
ある瞬間には誰が見ても自明な判断ができるようになります。
そのような能力がある人が社会でも重要な役割を果たすことができると思います。
Q. 瞑想で脳が変わるとどの程度持続しますか?
脳を変えるということは、ポジティブな感情を維持するように
脳の構造的な変化を起こさせるのでしょうか?
脳教育瞑想を平均3年5か月訓練したグループで一般グループと比較した時、
構造的な違いが発見されました。
この構造的な変化は感情調節及び集中力調節と関連があると思われます。
この研究に参加した実験グループは、
平均3年5か月間、週に4日、1日平均44分訓練してきたグループです。
短期間訓練したときの脳構造の変化を撮影していないため、
脳構造の変化が短期間で急速に起こる可能性を排除することはできません。
最近の研究結果は、その可能性が大きいことを示唆しています。
例えば、新しいゲームをさせた後、2時間後に脳の白質を撮ったら
白質が変わったという研究があります。
つまり、非常に短期間でも白質の変化が起こるということです。
しかし、脳は可塑性を持っているので、トレーニングによって
生活の質を向上させる方向に変化した脳も、
トレーニングをしなくなると変化が消えることがあります。
瞑想で脳の構造が変わるということは、この可塑性によって
神経回路が変わるということです。
変化した回路を維持するためには、トレーニングを続けなければなりません。
良い状態を維持するためには地道な努力が必要です。
Q. 大人の脳が変化するとおっしゃいましたが、
では、成長する子どもの脳もこのような瞑想によって
影響を受けるのでしょうか?
はい。私たちの研究チームで、瞑想が思春期の脳の発達に及ぼす影響について
研究結果を報告したことがあります。
青少年参加者をランダムに2つのグループに分け、一方のグループは毎日9分ずつ3週間瞑想を行い、
他のコントロールグループと作業記憶およびそれに関連する脳波の変化を比較調査したものです。
研究を通じて、瞑想を実行した青少年が統計的に有意に作業記憶が向上しており、
それに関連する脳波が変化していることが発見されました。
したがって、質問に対する答えを再確認すると、
子どもの脳もこのような瞑想によって変化すると見ることができ、
まだ青少年の時期については多くの研究が行われていないため、
今後関連する深い研究が行われる必要があると思われます。
Q. 脳が変化することはよくわかりましたが、
健康全般とはどのような関係があるのでしょうか?
脳は、私たちの体の他の部分とも密接につながり、その機能を調節しています。
脳で起こる変化は、神経系によって、または内分泌系を介して
血液によって体全体に情報が伝達されます。
したがって、瞑想が精神衛生だけでなく、身体的な健康にも影響を与えることが予想できます。
現在までに世界中で瞑想に関する多くの研究が行われており、
その研究で特に共通して多く報告されているのは、不安、ストレス、疲労、痛みの減少と、
睡眠の質、生活の質、気分の改善などです。
また、血圧や更年期症状を減少させるという報告や、その他にも様々な健康に関する報告があり、
高齢の成人において老化を遅らせるという報告があり、
老化に関連する疾患の予防に関する部分も今後期待されています。
Q. インドネシアのソブノス大学、
インドのヒンドゥスタン工科大学とMOUを結び、
このような瞑想講座を開設すると聞きました。
これからの抱負をお聞かせください。
兼任教授としているグローバルサイバー大学の脳教育融合学科で
「脳教育瞑想」という科目を担当することになりました。
「脳教育瞑想」とは、韓国の伝統的な瞑想を現代化し、
一般人も簡単に自分の体と心を管理できるように体系化した瞑想法です。
この講義は、グローバルサイバー大学が教育部事業として
韓国式瞑想に関する科目を韓国語版、英語版で制作したものです。
グローバルサイバー大学で脳教育瞑想に関するこの科目を海外10の大学に輸出し、
韓国の伝統文化をグローバル化したいというビジョンを持っています。
Q.現在、国際脳教育総合大学院大学の
統合ヘルスケア学科の学科長を務めていますが、
今後の抱負をお聞かせください。
統合ヘルスケア学科では、今後、脳教育瞑想に対する開かれた教育と研究を通じて、
健康について広い視野を持ってアプローチする専門家を育成したいと考えています。
特に、今後2025年、韓国は人口の20%以上が65歳以上の超高齢社会への突入を目前に控えています。
このような社会的変化に備えるため、
老化に関連する疾患を予防できる瞑想を取り入れた
様々な健康プログラムを開発・研究したいと考えています。
2023年3月21日(火・祝)20時~
ヤン・ヒョンジョン国際脳教育総合大学院大学統合ヘルスケア学科学科長の
講座はこちら→ 科学的な研究結果に見る脳教育の効果とメカニズム
Dr.Yangの脳のはなし Youtube再生リスト↓
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwqVKo3W_0oPU4IcPQhCy60RUEtGqmzvf